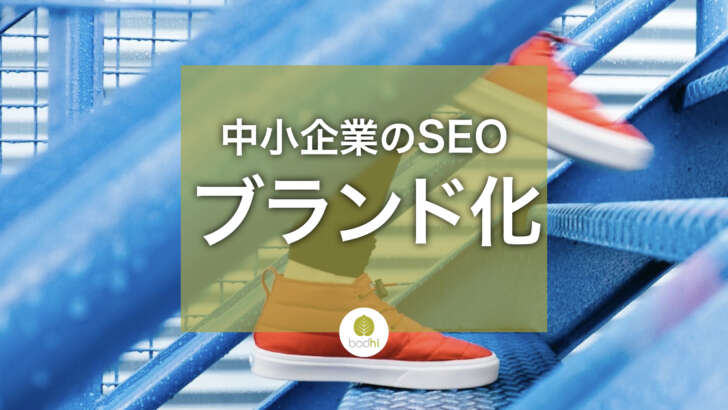現在のSEOにおいてブランディングは必須の要件です。Googleなどの検索エンジンがブランドを重視する傾向はますます強まってきているからです。大企業だけでなく中小企業も、サイトや会社、そして専門家としての社長自身について、知名度と信頼を積み上げる取り組みが必要です。
現在のSEOはブランドの勝負
SEOとブランドの間には非常に強い相関があります。確立されたブランドを持つサイトは、指名検索され、検索結果上でのクリック率が高く、サイト上での滞在時間が長く、ポジティブな言及や被リンクを集めます。これらのすべてがシグナルとなって、検索結果の順位をさらに押し上げます。
現在のSEOでは、ウェブサイトやコンテンツ制作者を、人々によく知られ、話題にされ、信頼されるブランドとして確立する必要があります。これが不十分な場合、たとえば指名検索が十分に得られていないサイトでは、コアアップデートのたびに順位が低下する現象も報告されています。
大企業が大きな予算を投じて実施する大々的なブランディングを想像すると、中小企業にとっては無関係なものに思えますが、中小企業であっても身の丈からの着実な取り組みとしてブランディングは実施できます。あなたの地域またはあなたの業種という範囲の中で知名度と信頼を積み上げていくだけだからです。
中小企業のブランディングは地域を限定するか特定分野に特化することが有効です。全国を視野に幅広い分野を狙えば、大手や中堅と直接競合してしまって不利です。弱者のSEO戦略を採りましょう。
コンテンツSEOだけではすぐに限界がくる
コンテンツを作り込むことによるSEOには限界があります。有用で高品質なコンテンツを継続的に制作すれば、当初は順調に検索流入を増やすことができます。しかし検索順位の上昇はどこかの時点で止まります。そのとき、より上位にいるのは、そのトピックにおけるブランドとして知られる有力なサイトです。
私たちは、自分のサイトや自分の会社や自分自身を、特定のトピックにおけるブランドに育てていく必要があります。コンテンツがGoogleに信頼され上位に表示されるためには、サイトやコンテンツ作者が、人々に実際によく知られ、話題にされ、選ばれ、信頼されていなければなりません。
サイトの評判の不正使用はブランド重視の裏返し
2024年5月からGoogleによる対応が本格化した「サイトの評判の不正使用」は、Googleがブランドを極めて強く重視することの裏返しです。サイトの評判の不正使用とは、すでにブランドが確立されたサイト上に第三者のコンテンツを置くことでランキングを操作することをいい、Googleは次のように説明しています。
サイトの評判の不正使用とは、ホストサイトにおいて、基本的にファーストパーティのコンテンツによってすでに確立されたランキング シグナルを利用することを主な目的として、そのサイトにサードパーティのコンテンツを公開する行為を指します。これは、サードパーティが独自に公開する場合に比べて、当該のコンテンツがより上位にランク付けされるようにすることを目的としています。
Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー | Google 検索セントラル1
ブランドが発するランキングシグナルは極めて強力です。だからこそ不正使用が横行し、Googleは対応の必要に追われています。また、こちらは不正使用ではありませんが、強力なブランドを持ったサイト(例えばLinkedIn2やnote3など)の配下にコンテンツを置くことで上位に表示されやすくなる状況は現在も続いています。
不正な方法であるか正当な方法であるかに関わらず、宿主サイトのブランドに寄生することで自分のコンテンツのランキングを上げることに成功したとしても、借り物のブランドはあくまで借り物に過ぎません。自分のサイトのブランドを強力なものにすることが理想です。
なぜGoogleはブランドを重視するのか
白書「Googleはどのように偽情報と戦っているか(PDF・英語)4」によれば、ウェブ検索はスパムや偽情報との戦いであるといいます。Google検索のアルゴリズムは権威があり信頼性の高い情報を優先するように設計されていて、その仕組みによってスパムや偽情報を排除するのです。
サイトの権威性や信頼性は、被リンクや指名検索やユーザー行動やサイテーションなど、実際の人々による評価で決まります。サイトが実際の人々に信頼されているブランドであれば、そこで発信されている情報はスパムや偽情報ではない、とGoogleは判断します。前出の「サイトの評判の不正使用」はこれを逆手にとってスパム判定を免れようとしたものです。
近年では生成AIの利用が進んでいますが、これらもGoogle検索と同様、スパムや偽情報に対処する必要があるものと考えられます。そのときGoogle検索と同様の対応方法が採られれば、やはり情報源となるサイトやページはブランドを重視したものとなるでしょう。生成AIにおすすめしてもらうためにはブランドが必要となるのです。
情報源からスパムや偽情報を取り除きたいのは生成AIも同じです。生成AIもまた「人々から信頼されているブランド」を信頼する方向性を強めていくでしょう。AI時代を見すえてもブランド化は急務です。
ブランディングの対象は自社と関連エンティティ
ブランディングの対象になるのは御社や御社が所有するブランドなど、指名検索やサイテーションの対象になるもの(つまり検索エンジンがエンティティとして認識可能なもの)すべてです。代表的なのは次のものですが、このほかにも独自のブランド名のついた製品ラインがあるならそれもブランディングの対象となります。
- 社名
- 店名(複数の店名があるならそのそれぞれ)
- サイト名(複数のサイトがあるならそのそれぞれ)
- 社長名
- コンテンツ著者名(複数の著者がいるならそのそれぞれ)
これらのうちたったひとつを人々に覚えてもらうだけでも大変なことです。中小企業や個人のように経営資源が乏しいケースでは、ブランドを乱立させないようにすることが大切です。おすすめは「社名=店名=サイト名」とし、「社長=コンテンツ著者」とすることです。こうすることで、ブランディングの効率を最大化できます。
一社で複数のサイトを運営していたり、ブランド名のついた製品ラインを複数持っていたりするケースはよくありますが、可能なら統合していくことをおすすめします。ブランドとして育てるエンティティが少なければ少ないほど、ひとつのエンティティに投下できる経営資源が増えるからです。
筆者自身のブランディングの取り組み
一例として筆者がブランディングに取り組んでいるのは、自社とこのサイトを表す「ボーディーSEO」のエンティティと、コンテンツ著者である「住太陽」のエンティティの2つだけです。筆者は自分一人だけでサイトを運営している零細企業オーナーですので、多数のエンティティをブランディングするのは不可能で、少数に絞って取り組んでいます。
それら2つのエンティティをブランディングすることの目標はキーワード「SEO」での検索結果で1ページ目に安定して表示させることです。このキーワードの上位には上場企業やSEO専業の中堅企業、Googleの公式やWikipediaの記事などがひしめいていて一人運営のこのサイトには厳しい環境ですが、うまくやりおおせることができたら痛快です。
一人運営で手間や時間に余裕がありませんので、サイトのコンテンツ量は諦めて、質だけを追うようにしています。また個人としては、依頼された講演は基本的に断らず、Web担当者Forumで連載を持つなど、専門家としての講演や執筆の機会をできるだけ多く持てるように努めています。この結果、目標まであと一歩のところまできています。
一人で運営しているような小規模なサイトが不利なのは事実ですが、着実にブランド化に取り組めば、極めて競争の激しいキーワードでもある程度は戦えます。
獲得したいブランドシグナル
通常、ブランディングの取り組みはその成果が漠然としていますが、SEOという目標を持つことで、ブランディングに中間指標を持たせることができます。ブランドとして人々に認知されていくにつれて増えてくるシグナルがあるためです。ここではそうしたブランドシグナルに注目します。
あるエンティティが人々の間でブランドとして確立されれば、人々はそのブランドを指名検索し、ブランドのサイトを訪れ、話題にし、リンクするでしょう。そうした人々の行動のすべてがシグナルになって、ブランドのエンティティは強化されます。Google検索が用いていることが明らかになっている主要なブランドシグナルは次のものです。
指名検索
指名検索とは、社名やサイト名、コンテンツ著者名などのキーワードを含む、ナビゲーショナルな意図の検索のことをいいます。例えば「ナイキ + スニーカー」や「Amazon + USBメモリ」や「スタバ + メニュー」などの検索が該当します。指名検索されることは、その対象に知名度と検索ニーズがあることを証明します。
指名検索で訪れたユーザーは「そのサイトに訪問する動機」のあるユーザーですから、直帰率が低く、サイト滞在時間が長く、コンバージョン率が高いなど、良好なユーザー行動シグナルを発し、サイト全体の検索順位を引き上げます。またGoogleは指名検索を特定のブランドへの支持投票として機能させる特許を有しています。
ユーザー行動
Google検索は検索結果画面上でのクリック率や、クリック後のサイト上での滞在時間、ユーザーが検索結果に戻ってきたかどうかなどのユーザーの行動を機械学習し、順位に反映します。ユーザーが満足したことが示唆される行動をとった検索結果はよい検索結果で、ユーザーが満足しなかったことが示唆されれば、それは悪い検索結果です。
よく知られ信頼されているブランドは、よいユーザー行動を導きます。商品を検索する人の70%は、検索結果の上位に表示された小売店よりも、自分がすでに知っている小売店(例えばAmazonのような)の結果を優先的にクリックすることが、Search Engine Land と SurveyMonkeyが実施した調査5で明らかになっています。
また米Page One Power社の調査6によれば、検索結果に表示されたリンクのクリックを促進する理由として、アメリカ人の59%は知っているブランドであることを重視する一方で、上位にランクされていることを重視する人は3分の1未満でした。ユーザーはアルゴリズムよりもブランドを信頼する可能性が2倍高いことを示しています。
サイテーション
サイテーションとはウェブ上で対象となるブランドが言及されることを指します。官公庁や大手ニュースサイトなど権威性が高く信頼されているサイト上でブランドが言及されることは、そのブランドが言及に値する重要なものであることを証明します。また、同時に言及された他のエンティティとの関連もGoogleは理解します。
SNSなどで展開される一般の人々によるブランドへの言及(クチコミ)も重要なサイテーションです。これらのクチコミによって初めてそのブランド名を目にする人が増えることに加え、その話題のブランドについて知るために指名検索をしたり、サイトに訪問してコンテンツを熟読する可能性が高まるためです。
被リンク
被リンクは外部のウェブサイトから受け取るリンクです。Googleなどの検索エンジンはリンクをあるページから別のページに対する一種の支持投票のように扱い、より多くのリンクを集めるページを重要なものとみなします。また同時に、より重要なページからのリンクをより重要なものとみなします。
リンクは信頼性や権威性を測る指標として用いられます。また、リンクは推薦や参照の意味で設置されることが多いため、よく知られていて信頼されているブランドほど、さらにより多くのリンクを集めます。被リンクを構築する意味でも、確立されたブランドは有利に働くのです。
実施するブランディング施策
SEOにおけるブランディングの目標は、ブランドを覚えてもらい、信頼してもらい、話題にしてもらうことです。これはブランディングの全体像からすればごく一部に過ぎませんが、全体的なブランディングを実施していくにあたっての中間目標として取り組んでいくのがよいでしょう。
識別しやすいブランド名をつける
サイテーションが機能するためには、あなたやあなたの会社が外部から言及を受けたとき、それがあなたやあなたの会社に対する言及であると検索エンジンが認識できる必要があります。他と重複しない社名、サイト名、コンテンツ著者名であれば最善ですが、実際にはそうもいかないことが多いでしょう。
同名の会社やサイトや人物がいる場合には、所在地や業種名など他と区別できる情報を常に付加するようにしましょう。例えば「アシスト」のようなよくある社名だった場合、常に「横浜のシステム開発 アシスト」や「京都の土木建築 アシスト」などと名乗るようにします。
もし会社名やサイト名をこれから考えるのであれば、他と重複しにくいことに加えて、読みやすく、覚えやすく、発音しやすく、聞き取りやすく、入力しやすい、といったことも考慮すべきです。外国語や当て字など、読めない、覚えられない、入力できないブランド名では、サイテーションや指名検索の獲得において損をします。
あなたやあなたの会社を単なる文字列ではなく実体(エンティティ)として検索エンジンに認識させることを意識しましょう。
コンテンツの著者情報を明示する
コンテンツごとに、そのコンテンツに責任を持つ人物の個人名と連絡先を表示しましょう。コンテンツの著者はそのトピックの専門家としてブランディングしていく対象です。実在する専門家として名前と顔を出した著者情報を表示することはE-E-A-Tの観点から必須です。
コンテンツ制作者のエンティティを専門家として検索エンジンに認識させるためには、マスメディアなどから取材を受けたときに名前の出る人物、つまり取材内容が記事化されたときにサイテーションを受ける人物が、コンテンツの著者として表示されていることが理想です。中小企業ならほとんどの場合、これは社長の役割です。
ただし、実際に社長自身が制作したのではないコンテンツ、たとえば他の社員や外部のライターが制作したコンテンツを、社長の名義で発表するのは感心しません。社員が制作したコンテンツはその社員の責任で記名すべきですし、社長は自分の名義で発表するにふさわしいコンテンツを自作すべきです。
クチコミ投稿をお願いする
ローカルビジネスではGoogleビジネスプロフィールのクチコミ投稿を獲得すること、ECサイトでは購入者による商品レビュー投稿を獲得することで、御社のE-E-A-Tが向上します。地域密着のローカルビジネスとECサイトでは、クチコミ投稿の獲得は他のどんな施策よりもSEOに効果的です。
とはいえ飲食店など一部の例外を除けば、お願いしないとクチコミ投稿は増えません。口頭で直接お願いすることはもちろん、ポップなどの掲示物やチラシやショップカードなどの配布物を使ったり、ECサイトなら同梱物やフォローアップメールを使うなどして、クチコミ投稿をお願いするようにしましょう。
ただし、Googleビジネスプロフィールのクチコミ投稿に対して金銭や物品などのインセンティブをつけることは、Googleマップの投稿コンテンツに関するポリシー ヘルプ7に違反します。クチコミ投稿に何らかの対価を支払うことはせず「単にお願いするだけ」にするようにしましょう。
SNSでコミュニティと交流する
個人を認知してもらうにあたっては、X8のようなSNSの活用は欠かせません。自分の専門分野に関心のある人々とつながり、そこでの存在感を高めることで、認知を広げるとともに、コンテンツを発信するときには拡散も期待できます。Googleも公式ブログで次のように述べています。
そのサイトのテーマに関連するコミュニティに積極的に参加することが、サイトの評判を上げ、良質なリンクを得るのに有効です。フォーラムやブログなどで、意見やコメントを投稿し、参加ユーザーと交流してみましょう。
良質なリンクを得るには | Google 検索セントラル ブログ9
SNSは個人同士が交流するのに適した場です。会社の公式アカウントは交流には向きません。個人のアカウントで、個人としてSNSに参加することが基本です。公式アカウントの運用はうまくいかず、社長の個人アカウントのほうがうまくいっている、というのは当然の結果です。
とはいえ、私的な日常をつぶやいたり見知らぬ他者と交流することに躊躇してしまって、SNSの活用が苦手だという人も多いと思います。実は筆者もそんな一人です。そんな場合には「仕事として、仕事に関連することだけつぶやき、頻度も上げない」と割り切ってしまうのも一つの方法です。筆者のXもそのように運用しています。
メディア向けの広報活動をする
マスメディアや地域メディアなど、権威あるメディアへの露出を狙った広報活動を実施します。「(地域または業種)で初めて」や「(地域または業種)で一番」や「いま話題の○○」のような形の報道価値のある話題を作ってプレスリリースを配信しましょう。権威あるメディアに扱われれば強力なサイテーション効果が得られます。
なお複数の記者の証言として、報道価値のない単なるお知らせでプレスリリースを乱発しているようなスパムまがいの会社(残念ながら大量に存在します)のリリースは自動的に無視するといいます。パブリシティを狙うなら、報道価値(ニュース性)のあるリリースだけを配信するようにしましょう。
たくさんのお客さまを満足させる
この項の冒頭で「SEOにおけるブランディングの目標は、ブランドを覚えてもらい、信頼してもらい、話題にしてもらうこと」と述べました。これらを実現するための最も確実な方法は、より多くの人々にお客さまになってもらい、御社の製品やサービスを実際に使っていただき、満足していただくことです。
熱心なクチコミや評判は満足してくださったお客さまから生まれます。満足してくださったお客さまを増やすことこそが、最も確実なブランディングです。そのために広告を使うのもいいですし、社長が広告塔となって既存メディアやSNSやYoutubeで露出するのもいいでしょう。方法はたくさんあります。
地域のイベントに協賛したり、地域の学校の社会見学や行政の視察を受け入れたり、業界団体での役職を引き受けたり、国の助成事業で官公庁と協力関係を築いたりすることで、メディアでの露出を増やした例もあります。露出機会を増やし、お客さまを増やすことのすべてが、ブランディングにつながります。自社に合った取り組みを探しましょう。
まとめ
中小企業のブランディングで目指すのは、地域か業種を絞り、その範囲内での知名度と信頼を獲得することです。その結果として、指名検索や、良好なサイテーション(言及)やレピュテーション(評判)やユーザー行動、そして被リンクを獲得していきます。これらは着実な積み上げが可能で、あとはやるかやらないかだけです。
ことSEOの観点からは、ブランディングは必須の要件です。信頼されていない無名のサイトに集客することはますます困難になってきています。あなたの会社やサイトと、専門家としてのあなた自身を、ブランドとして確立しましょう。そして最も大切なことは、こうしたブランディングはSEOがなくても生き残りのためにやるべきことだということです。
ブランディング施策はその効果や進捗の評価が難しいものですが、SEOはいい評価指標になります。上位表示を目指しながらブランドを強化していきましょう。
脚注
- Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー | Google 検索セントラル ↩︎
- LinkedIn ↩︎
- note ↩︎
- How Google Fights Disinformation(PDF・英語) ↩︎
- Brand Bias: 70% Of Consumers Look For Known Retailers When Doing Product Searches ↩︎
- Navigating Digital Trust: What Makes Information Reliable? | Page One Power ↩︎
- 禁止および制限されているコンテンツ – マップユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー ヘルプ ↩︎
- 「いま」を見つけよう / X ↩︎
- 良質なリンクを得るには | Google 検索セントラル ブログ ↩︎
 住 太陽
住 太陽